- 消費者問題について弁護士に相談
- 弁護士コラム
- 内金が返金されないのはなぜ? 頭金、手付金との違いは? 弁護士が回答
内金が返金されないのはなぜ? 頭金、手付金との違いは? 弁護士が回答
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
内金の性質は契約によって異なるので、契約書の内容を精査する必要があります。対応に困ったら、弁護士にアドバイスをお求めください。
本記事では内金について、概要や性質、返金されない場合の対処法などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、内金とは?
「内金」とは、契約を締結するに当たって、代金などの一部として支払うお金のことです。「前金」「頭金」「申込金」「申込証拠金」「預かり金」などと呼ばれることもあります。
たとえば、成人式のためのヘアメイクや着付けを申し込む際には、内金として代金の一部を支払うよう求められるケースがあるでしょう。
マンションや戸建てなどの不動産、自動車などの高額な財産を購入する際にも、売買代金の一部を内金として支払うのが一般的です。
このように、内金のやりとりは幅広い取引について行われています。
-
(1)内金の目的
契約を結ぶに当たって、売り手側が内金の支払いを求める背景には、主に以下のような目的があります。
- 買い手側に対し、真剣に契約を締結することを求めるため
- 買い手側に資力があることを確認するため
- 買い手側の都合で契約をキャンセルされた場合に、違約金として没収するため
-
(2)内金の性質は、契約によって異なる
内金が法的にどのような性質を持っているかは、それぞれの契約の定めによって決まります。
たとえば、契約を解除した際に内金は返還されるのか、内金を放棄して契約を解除する権利があるのかなどの取り扱いは、各契約内容に左右されます。
従って、内金の支払いを求められた際には、契約書において内金がどのように定められているかをきちんと確認すべきです。内金の取り扱いがよくわからない場合は、支払いを拒否することや、契約自体を取りやめることも検討しましょう。
万が一、内金が返還されないなどのトラブルが発生した場合には、契約の定めを踏まえて対応する必要があります。弁護士や消費生活センターなどに相談してアドバイスを求めましょう。 -
(3)内金と手付金の違い
内金と同じく、契約締結時において買い手が売り手に支払う「手付金(手付け)」には、法律上の効果があります。
手付金とは、売買契約など有償契約を結ぶ際に、買い手側が売り手側に対して渡す金銭です。手付金には、以下の3つの性質があると解されています。① 証約手付
契約が成立したことを証明するためにやりとりされる手付金です。すべての手付金は、証約手付の性質を持っています。
② 解約手付
買い手側が放棄するか、または売り手側が倍額を返すことにより、契約解除ができる効果がある手付金です。
手付金は原則として解約手付に当たりますが、契約を結ぶ際に解約手付とはしない、と定めることもできます。
③ 違約手付
買い手側の契約違反が発生した場合に、違約金として没収される手付金です。
手付金は原則として違約手付に当たらないのですが、契約で特に定められた場合には、違約手付となります。特に重要なのは、上記②の解約手付としての性質です。
手付を放棄または倍返しする点を除き、ペナルティーなしで契約を解除することができます(ただし売り手側が「契約の履行に着手」したあとは解除できません。)。
契約で「解約手付ではないこと」が明記されていなければ、手付金は解約手付としての性質を持っています。
内金と手付金の関係性や違いについては諸説ありますが、内金の性質が契約の定めによって決まる以上、その違いについて深堀りする実益は乏しいでしょう。
内金は、解約手付や違約手付と同様の効果が認められているケースもある一方で、証約手付と同等の意味合いしか与えられていないケースもあります。
内金がどのように取り扱われるかは、契約書の内容を確認しなければわかりません。
2、不動産取引の内金に関する規制
売り主が宅地建物取引業者(不動産会社など)であり、かつ買い主が宅地建物取引業者でない不動産の売買契約には、宅地建物取引業法の規制が適用されます。
宅地建物取引業法が適用される不動産の売買契約では、手付は必ず解約手付となります(同法第39条第2項)。
買い主は、売り主が契約の内容を実行し始めるまでの間、手付金を放棄して不動産の売買契約を解除することができます。この買い主の権利を排除または制限する特約は無効です(同条第3項)。
内金についても、実質的な観点から手付に当たると評価できれば、宅地建物取引業法に基づく上記の規制を適用する余地があると考えられます。その場合、買い主は内金を放棄することにより、不動産の売買契約を解除できます(なお、この場合は、当然、内金は返金されませんので、ご注意ください)。
内金について、宅地建物取引業法の上記の規定が適用されるかどうかは、契約の定めを精査しなければ判断できません。必要に応じて、弁護士のアドバイスをお求めください。
3、内金が返金されないなどのトラブルについて、弁護士ができること
事業者と締結した契約を解除した後、内金が返金されないなどのトラブルが発生した場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
事業者と間の契約トラブルについて、弁護士は主に以下のサポートを行っています。
-
(1)契約書のチェック
契約トラブルの処理は契約書の定めに従うため、まずは契約書の内容をきちんと確認する必要があります。
契約書の解釈に当たっては、法律の知識に基づく慎重な検討が必要不可欠です。
たとえば、契約書の文言上は内金を返還しないと定められていても、消費者契約法違反や公序良俗違反などによって、その定めが無効となるケースもあります。
弁護士であれば、返金を拒否する事業者に対する反論を、多角的な視点から検討できます。 -
(2)相手方との交渉の代理
弁護士は依頼者の代理人として、契約トラブルに関する和解交渉を行います。
事業者側から譲歩を引き出すためには、契約書に基づくルールや処理手順について、根拠を示して合理的な主張をすることが大切です。
弁護士がお客さまの代わりに和解交渉をすれば、事業者に対して法的な説得力を持ってこちら側の主張を伝えることができるため、有利な条件での和解成立が近づきます。
事業者側と和解する際には、和解合意書を残すことになります。
合意書作成に当たっては、合意した内容がきちんと反映されているかどうか、不明確な点がないかどうかを確認しなければなりません。
弁護士であれば、和解合意書の作成やチェックもできます。適切な内容で和解合意書を作成すれば、トラブルの再燃を防げるので安心です。 -
(3)訴訟を通じた返金請求
事業者側が内金などの返金を拒否し続けているときは、裁判所に訴訟を提起することも検討すべきです。
弁護士であれば、訴訟手続き全般について代理人として対応できます。複雑で注意点が多い訴訟手続きでも、弁護士であれば適切に対応可能です。
消費生活センターなどの窓口では無料で相談できますが、代理人として対応してもらうことはできません。
弁護士への相談や依頼は有料ですが、依頼者の代理人として、要望に従って迅速に対応してもらえることが大きなメリットと言えます。
4、弁護士に相談する際の流れと持ち物
事業者との契約トラブルについて弁護士に相談する際の流れと、持参するとよい持ち物について解説します。
-
(1)弁護士に相談する際の流れ
事業者との契約トラブルについて弁護士に相談する際の流れは、大まかに以下のとおりです。
① 問い合わせ
法律事務所のウェブサイトなどから、法律相談を申し込みます。日程や相談方法(対面・オンラインなど)について決めます。
② 法律相談
予約した日に、弁護士に相談します。弁護士は守秘義務を負っているので、相談内容が第三者に漏れることはありません。
正式に依頼した際の弁護士費用についても、弁護士から詳しく説明を受けます。
③ 委任契約の締結
弁護士による対応の内容や費用などについて納得できたら、委任契約を結んで正式に弁護士へ依頼します。依頼時に着手金を支払います。
④ 弁護士による対応
弁護士が調査・和解交渉・訴訟の提起などを行い、トラブルの解決を目指します。解決に至ったら依頼は終了となり、結果に応じて報酬金を支払います。 -
(2)相談時にあるとよい持ち物
弁護士に相談する際には、以下のようなものを持参するとよいでしょう。
- 相談内容や時系列をまとめたメモ
- 事業者と締結した契約書
- その他のトラブルに関連する資料
- 本人確認書類
- 印鑑
弁護士から事前に指示を受けた場合は、その指示に従って必要なものをご持参ください。
5、まとめ
内金の性質は契約書の定めによって決まるため、解除時に内金が返還されるかどうかは契約内容によって異なります。事業者に内金の返金を拒否されたら、まずは契約書の内容を精査したうえで対応を検討しましょう。
対処の仕方がわからないときは、弁護士に相談することも選択肢のひとつです。
ベリーベスト法律事務所は、事業者との契約トラブルに関する消費者のご相談を受け付けております(有料)。内金が返金されないことに納得できない方や、その他の契約トラブルにお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
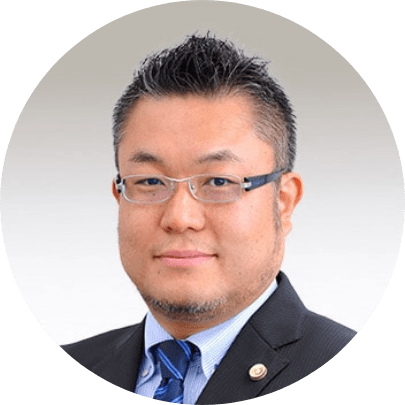
消費者トラブルへの知見が豊富な消費者問題専門チームの弁護士が問題の解決に取り組みます。
マルチ商法や霊感商法、悪徳商法などをはじめとした消費者トラブルでお困りでしたら、ぜひ、お気軽にご相談ください。