- 消費者問題について弁護士に相談
- 弁護士コラム
- 高額請求された場合、どこに相談する? どう対処すればいい?
高額請求された場合、どこに相談する? どう対処すればいい?
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
・ ぼったくりバーで高額請求をされた
・ 絶対にもうかると言われて高額のセミナーを受講したがまったくもうからない
消費者の無知や経験不足につけ込んだ、悪質な事業者による高額請求のトラブルが後を絶ちません。特定商取引法や消費者契約法などの法律では、悪質な消費者トラブルから消費者を保護するためにさまざまな規制をしていますので、高額請求の被害に遭ったときは、クーリングオフなどの手段で被害の回復を図ることができます。
もっとも、多くの方が何から手を付ければよいのかわからない状態でしょう。もしもトラブルに遭ってしまった場合には、まずは第三者に相談することをおすすめします。今回は、高額請求をされたときの相談先や対処方法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、高額請求されてしまった場合の相談先
事業者から高額請求されたというトラブルに遭ったときは、ひとりで抱え込むのではなく、すぐに以下のような相談先に相談しましょう。
-
(1)行政窓口
高額請求などの消費者トラブルを相談できる行政窓口としては、
・消費者ホットライン
・消費生活センター
などがあります。
消費者ホットラインは、消費者庁が設置している電話相談窓口で、専門の相談員が相談内容を聞き取って、解決のためのアドバイスをしてくれます。また、面談相談が必要な事案については、お近くの消費生活センターを案内してくれます。
消費生活センターでは、専門の相談員が直接相談に応じてくれますので、実際の資料などを踏まえて解決のためのアドバイスをしてくれます。
いずれも無料で相談することが可能ですが、アドバイスを踏まえて行動しなければならないのは消費者自身です。 -
(2)弁護士
弁護士は、さまざまなトラブルや法律問題を解決できる専門家ですので、高額請求といった消費者トラブルについても相談できます。
消費者問題に詳しい弁護士であれば、実際の事案を踏まえて適切な解決方法をアドバイスできますし、弁護士に依頼すれば事業者との対応もすべて任せることができます。
行政窓口とは異なり費用がかかりますが、自分で対応するのが難しいという方は、弁護士に相談・依頼した方がよいでしょう。
なお、相談する際の流れや注意点については、次章で詳しく説明します。
2、相談するとき、あるとよいものや注意点
高額請求のトラブルに遭った場合、すぐに弁護士や行政窓口に相談することが重要です。以下では、相談時に準備しておくべきものや注意点、相談の流れなどを説明します。
-
(1)高額請求トラブルの相談をする際に準備しておくべきもの
高額請求のトラブルを相談する際には、行政窓口でも弁護士でも以下のようなものがあるとよいでしょう。
- 契約書や約款、広告やパンフレットなど事業者から交付された書類
- ネット関係のトラブルであれば当該ページをプリントアウトしたもの
- 事業者とのやりとりがわかるメールやLINEの履歴
- トラブルの経緯や流れがわかるように時系列でまとめたメモ
一見そのトラブルとは関係がないように思われる資料であっても、トラブル解決に役立つことがありますので、自分で取捨選択をするのではなく、すべての資料を持参した方がよいでしょう。
なお、弁護士に相談する際には、身分証明書などの持参も必要になります。詳しくは相談予約をする際に確認しましょう。 -
(2)高額請求トラブルの相談の流れ
弁護士に高額請求トラブルの相談をする場合、以下のような流れで行います。
① 消費者トラブルに詳しい弁護士を探す
弁護士によって得意とする分野が異なりますので、高額請求に関するトラブルは消費者問題を取り扱う弁護士に相談するべきです。
ご自身のトラブル解決を引き受けてもらえるかは、インターネットで検索して法律事務所のホームページを確認したり、電話で確認するのが良いでしょう。
中には、「詐欺に遭ったお金を必ず取り返す」と広告でうたいつつも、着手金だけ納めさせて何もしない、という法律事務所もあります。こうした事務所には、弁護士に相談できない、一人しか弁護士がいないのに24時間365日対応を謳っている、といった特徴があります。
事務所を探す際には、こうした事務所には注意しましょう。
② 弁護士事務所に連絡して法律相談の予約をする
弁護士への相談は、基本的には予約制になっていますので、いきなり弁護士事務所を訪ねても相談に応じてもらうことはできません。
そのため、まずは弁護士事務所に連絡をして、法律相談の予約を取るようにしてください。なお、クーリングオフという方法を用いる場合等、期限がある場合がありますので、弁護士に相談するならできる限り早い日時を予約した方がよいでしょう。
③ 予約した日時に弁護士事務所を訪れて法律相談を行う
法律相談の予約をした日時に弁護士事務所を訪れて、弁護士との法律相談を行います。
法律相談の時間は、1時間程度ですので、限られた時間内でトラブルの概要を理解してもらうためにも、トラブルの経緯を時系列でまとめたメモなどを持参するようにしてください。
④ 弁護士にトラブル対応を依頼する場合は委任契約を締結する
相談後、弁護士から解決方法をご提案します。提案内容に納得いただき弁護士に依頼する場合は、委任契約を結びます。
弁護士に依頼するには弁護士費用がかかりますので、事前にしっかり説明を求め、納得できた段階で契約するようにしましょう。
契約後は、弁護士が事業者との交渉や法的手段による対応に着手していきます。
3、高額請求された場合の対応策とは
高額請求されたときでもあきらめる必要はありません。以下のような方法を取れば、高額請求トラブルを解決できる可能性があります。どの方法を取るのが最適なのかは、1章の相談窓口に相談しましょう。
-
(1)クーリングオフ
クーリングオフとは、契約の申し込みまたは契約の締結後でも、一定期間内なら無条件に契約の申し込みの撤回または契約の解除ができる制度です。
「クーリングオフ」という言葉のとおり、消費者が頭を冷やして冷静になり、契約の必要性を再考する機会を与えることを目的とした制度になります。
クーリングオフができる取引形態と期間については、特定商取引法により以下のように定められています。
取引形態 販売方法 クーリングオフ期間 訪問販売 アポイントメントセールス、キャッチセールス、家庭訪問販売、職場訪問販売、展示販売、SF商法など 法定書面を受け取った日から8日間 電話勧誘販売 事業者が電話をかけて勧誘または消費者に電話をかけさせて勧誘するもの 訪問購入 事業者が営業所以外の場所で消費者から物品を購入するもの 特定継続的役務提供 家庭教師、学習塾、パソコン教室、語学教室、エステティックサロン、美容医療、結婚相手紹介サービスなど 業務提供誘引販売取引 いわゆる内職・モニター商法による取引 法定書面を受け取った日から20日間 連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法による取引 なお、クーリングオフの詳しい手順については、4章で説明します。クーリングオフできない取引形態に関しては、(2)以下の解決方法を取ることになります。
-
(2)相手方との交渉
高額請求の被害に遭った場合には、上記のクーリングオフにより契約の解除、返金が可能な場合もありますが、クーリングオフできない契約形態だったり、悪質な業者だと素直に応じてくれないケースもあります。その場合には、相手方との交渉により返金を求めていかなければなりません。
また、クーリングオフ期間が経過してしまったとしても、消費者契約法や民法に基づく取消権を使うことで、取引の巻き戻しを主張することが可能です。その場合も相手方との交渉が必要になりますので、自分で対応するのが不安なときは弁護士に依頼するのがおすすめです。 -
(3)あっせん
あっせんとは、公平中立な第三者が当事者の間に入って交渉の仲介をし、和解による紛争解決を図る制度です。消費生活センターでは、あっせんによるトラブル解決制度を設けていますので、消費生活センターに相談した際には、あっせんの利用も検討してみるとよいでしょう。
ただし、あっせんは合意による紛争解決制度ですので、事業者があっせんに応じない、交渉で合意に至らないような場合には、終了となります。 -
(4)少額訴訟
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを請求する場合に利用できる、簡易裁判所の裁判手続きです。原則として1回の審理で判決が言い渡されるため、通常訴訟に比べて簡易かつ迅速な解決が期待できます。
少額訴訟であれば、通常訴訟のような複雑な手続きは必要ありませんので、被害を受けた消費者自身で手続きを進めることもできます。 -
(5)通常訴訟
事業者との交渉で解決できないときは裁判所に訴訟提起をすることになります。
少額訴訟とは異なり通常訴訟の手続きは、非常に複雑かつ専門的で、知識や経験に乏しい一般の方では適切に対応するのは難しいものです。
そのため、訴訟による解決が必要な場合については、自分で対応するのではなく弁護士に依頼するようにしましょう。
4、高額請求され、クーリングオフする場合の手順
もしクーリングオフがトラブルの解決にもっとも適切な方法であるとわかったら、期間内に手続きを行いましょう。クーリングオフは、郵便などの書面または、メールなど電磁的記録による方法で行います。以下では、クーリングオフの具体的な手順を説明します。
-
(1)クーリングオフを書面で行う方法
書面でクーリングオフを行う場合、以下の事項を記載したハガキを利用する方法が一般的です。
- 契約年月日
- 商品名
- 契約金額
- 販売者
- 契約を解除する旨
- 作成年月日
- 消費者の住所、氏名
ハガキに上記事項を記載後は、両面をコピーしておき、「簡易書留」または「特定記録郵便」で送るようにしてください。
-
(2)クーリングオフを電磁的記録で行う方法
電磁的記録でクーリングオフを行う場合、専用フォームがあるなら、そこからクーリングオフの通知を行います。また、専用フォームがないなら、以下の事項を記載したメールを事業者に送信してクーリングオフを行います。
- 契約年月日
- 商品名
- 契約金額
- 販売者
- 契約を解除する旨
- 作成年月日
- 消費者の住所、氏名
なお、専用フォームの画面をスクリーンショットで保存またはメールを保存するなどの方法でクーリングオフをしたことの証拠を残しておきましょう。
5、まとめ
高額請求の被害に遭ったとしても適切な対応を取ることで被害の回復を図ることができる可能性があります。
しかし、そのためには知識や経験豊富な第三者によるアドバイスが不可欠となりますので、分からないことがある場合は、行政窓口や弁護士に相談することがおすすめです。高額請求された場合の相談先は、有料・無料共にありますが、取れる手続には期限のあるものもありますので、相手方との契約に納得がいかない場合にひとりで悩むのではなく早めに第三者に相談するようにしましょう。
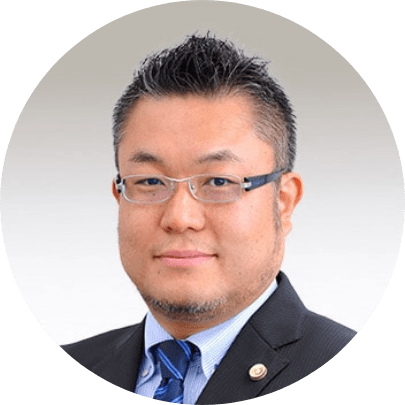
消費者トラブルへの知見が豊富な消費者問題専門チームの弁護士が問題の解決に取り組みます。
マルチ商法や霊感商法、悪徳商法などをはじめとした消費者トラブルでお困りでしたら、ぜひ、お気軽にご相談ください。