- 消費者問題について弁護士に相談
- 弁護士コラム
- 高額な離檀料を請求されたら、どう対処する? 弁護士が解説!
高額な離檀料を請求されたら、どう対処する? 弁護士が解説!
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
そもそも離檀料とはどのような性質のお金なのでしょうか。また、お寺から高額な離檀料を請求された場合、どのように対処すればよいのでしょうか。
今回は、離檀料の法的性質と高額な離檀料を請求されたときの対処法について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、離檀料って払わないといけないの?
檀家をやめる際に離檀料を請求されることがありますが、そもそも檀家制度とはどのようなものなのでしょうか。以下では、檀家制度の概要と離檀料の法的性質について説明します。
-
(1)檀家制度とは?
檀家制度とは、檀家が特定の寺院(菩提(ぼだい)寺)に所属し、法事・葬儀・供養などの宗教的サービスの提供を受ける代わりに、お布施などにより寺院を経済的に支援する制度です。
- 檀家:特定の寺院に所属し、先祖の供養や方法などを依頼する家
- 菩提寺:檀家の先祖代々の供養を行う寺
このような檀家制度は、江戸時代に制定されたものであり、幕府がキリスト教の禁止と民衆管理のために戸籍代わりに登録させたのが始まりです。現在は、檀家制度は法的制度ではなくなりましたが、多くの家庭が菩提寺との関係を持ち続けています。
しかし、近年では、檀家をやめ墓じまいするなど寺離れが進んでいると指摘されています。 -
(2)離檀料の法的性質
離檀料とは、檀家が自分の所属する菩提寺との関係を絶つ(離檀)する際に、寺に対して支払うお金のことをいいます。
離檀料は、先祖供養を長年続けてきたことへの対価や墓じまいなどに伴う、手続きの手間への謝礼としての性質を有しており、法的根拠はありませんが慣習として認められているものです。
離檀料の金額としては、数万円から数十万円程度が一般的ですが、金額に明確な基準はありません。その寺院や地域、寺との関係性などで金額が異なるため、事前の確認が必要です。
このように離檀料の支払いは法的義務ではないため、離檀料を請求されても断ることができます。しかし、裁判になると請求された離檀料がそれほど高額でなければ、慣習を根拠として支払いが命じられる可能性もあります。 -
(3)離檀料に関する注意点
菩提寺から請求されたのが離檀料ではなく、未納だった管理料であった場合には、檀家には支払い義務がありますので、どのような性質のお金なのかをよく確認するようにしてください。
また、離檀に伴う墓石の撤去や新設、閉眼供養などにも費用がかかるため、事前に確認が必要です。
2、離檀料のトラブルの相談先とは
高額な離檀料を請求されたなどの離檀料に関するトラブルに巻き込まれたときは以下のような相談先に相談してみるとよいでしょう。
-
(1)所属する宗派の本山・檀家総代
菩提寺から高額な離檀料を請求されたときは、菩提寺が所属する宗派の本山に相談してみましょう。あまりにも高額な離檀料だと理解してもらえれば、寺院内部での解決が期待できます。
また、檀家総代との関係が良好であれば檀家総代に相談してみるのも有効な手段です。檀家個人の話には応じなかったとしても、檀家総代から説得されれば菩提寺も離檀料の減額に応じてくれる可能性があります。 -
(2)石材店
離壇に伴いお墓の新築や改装、墓じまいなどをするために石材店にお世話になることがあります。石材店は、離壇に関するトラブルを多く経験していますので、石材店に相談をすればこれまでの経験を踏まえて円満な解決方法をアドバイスしてくれるかもしれません。
-
(3)消費生活センター
菩提寺と檀家との間の離檀料に関するトラブルは、消費者トラブルの一種ですので、消費生活センターで相談することができます。
消費生活センターでは、離檀料のトラブルに関する相談事例が複数ありますので、過去のトラブルを解決した経験などに基づいて適切なアドバイスをしてくれるはずです。
消費生活センターでの相談は、無料ですので、お金をかけずに相談したいなら消費生活センターを利用してみるとよいでしょう。 -
(4)弁護士
弁護士は、さまざまな法律問題やトラブルを取り扱う専門家ですので、菩提寺と檀家との間の離檀料に関するトラブルについても相談可能です。
法律の専門家である弁護士に相談すれば法的観点から離檀料のトラブルを解決するためのアドバイスをもらうことができ、菩提寺との対応に悩むときは弁護士に代理人として対応してもらうこともできます。
ただし、弁護士に相談をするには、基本的には有料になりますので注意が必要です。
ご自身の置かれている環境によって最適な相談先は異なります。ご自身のケースに合った相談先を選びましょう。
3、離檀料トラブルの解決法
離檀料に関するトラブルが生じたときは、以下のような方法で解決を図ります。
-
(1)お寺との話し合い
菩提寺から高額な離檀料を請求されるなどのトラブルが生じた場合、まずは2章で紹介した相談窓口で相談した上で、トラブル解決に向けたお寺との話し合いをスタートします。
離檀料を支払う法的な義務はないため、「離檀料は支払いません」という態度を示すことも可能ですが、円満な解決を希望するのであれば、離檀料の相場程度の金額は支払う姿勢を示した方がよいでしょう。
長年お世話になったことへの感謝の気持ちを示すことで、菩提寺も高額な離檀料の請求を諦めてくれる可能性があります。 -
(2)遺骨返還請求訴訟を提起する
菩提寺との話し合いが決裂すると「離檀料を支払わなければ、埋蔵証明書を出さない」と言われてしまうことがあります。埋蔵証明書とは、遺骨がその寺に納められていることを公的に証明する書類です。(自治体によって書類の正式名称は違いますので、詳しくはご遺骨のある自治体にご確認ください)
遺骨を別のところに移動する際にはこの書類が必要になります。埋蔵証明書がなければ改葬ができず、遺骨を引き渡してもらえなければ手元供養をすることもできなくなってしまいます。
このような状況になったときは、菩提寺に対して、最終手段として遺骨返還請求訴訟を提起するとよいでしょう。故人の遺骨の所有権は遺族(祭祀(さいし)承継者)にありますので、裁判になれば基本的には檀家側の請求が認められるでしょう。
そのため、裁判を起こすという態度を示せば、裁判になる前に菩提寺との話し合いで解決となる可能性もあります。
4、改葬の強行は、おすすめできない
改葬とは、埋葬されている遺骨を別の墓地や納骨堂などに移す手続きです。
菩提寺から高額な離檀料を請求されて納得ができないからといって、改葬を強行するのはおすすめできません。
-
(1)改葬を強行すると「埋蔵証明書」を発行してもらえないリスクがある
墓地使用者には、墓所への通行権や墓石の管理権があり、遺骨については祭祀承継者としての保持権が認められていますので、お寺の住職の許可がなくても改葬や墓じまいを強行することは事実上可能です。
しかし、実際には改葬や墓じまいにあたっては、自治体へ改葬許可申請をしなければなりません。その手続きにはお墓を管理する菩提寺から「埋蔵証明書」をもらう必要があります。
お寺の許可を得ずに改葬や墓じまいを強行しても、埋蔵証明書がもらえずに手続きがストップしてしまいますので、改葬の強行はおすすめできません。
基本的にはお墓を管理する菩提寺としっかり話し合いをして、お互いに納得した上で改葬や墓じまいの手続きを進めていくようにしましょう。 -
(2)改葬手続きの流れ
改葬をする際の手続きの流れは、以下のとおりです。
① 移転先の墓地・納骨堂の確保
まずは、新たに遺骨を納める場所を探して、契約をします。
② 改葬許可申請書の取得
現在、遺骨が埋葬されている役場から「改葬許可申請書」のひな型をもらいます。
お住まいの役場によってはウェブサイト上からダウンロードできるところもあります。
③ 菩提寺から埋蔵証明書を取得
菩提寺から遺骨が埋葬・納骨されていることを証明する「埋蔵証明書」をもらいます。
菩提寺との関係が良好であれば、特に問題なく発行してもらえますが、離檀料の支払いでもめている場合は、埋蔵許可証の取得も難航する可能性があります。
④ 移転先の墓地・納骨堂から受入証明書を取得
移転先の墓地・納骨堂から改葬により取り出した遺骨の受け入れを承諾していることを証明する「受入証明書」をもらいます。
⑤ 市区町村役場に改葬許可申請書などを提出する
②~④までで取得した書類や、そのほかその自治体で求められる書類を遺骨が埋葬されている市区町村役場に提出して、「改葬許可証」を発行してもらいます。
⑥ 遺骨の取り出し・改葬
改葬許可証が発行されれば、遺骨の取り出し・改葬が可能になります。
5、まとめ
離檀料は、法的には「謝礼」としての位置づけになりますので、檀家には離檀料を支払う法的義務はありません。そのため、高額な離檀料を請求されて金額に納得できないときは、離檀料の支払いを拒否することも可能です。
しかし、離檀料の支払いを拒否したことで菩提寺との対立が生じてしまうと、改葬や墓じまいに必要な「埋蔵証明書」を発行してくれない可能性もありますので、離檀料のトラブルは、基本的にはお寺との話し合いで解決するのが望ましいといえます。
ご自身で対応するのが不安な場合やお寺との話し合いでももめそうなときは、ひとりで解決しようとせず、第三者に早めに相談しましょう。
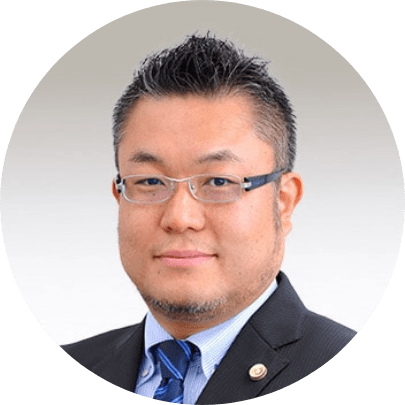
消費者トラブルへの知見が豊富な消費者問題専門チームの弁護士が問題の解決に取り組みます。
マルチ商法や霊感商法、悪徳商法などをはじめとした消費者トラブルでお困りでしたら、ぜひ、お気軽にご相談ください。