- 消費者問題について弁護士に相談
- 弁護士コラム
- これってねずみ講? 怪しい契約をしてしまった場合の対処法
これってねずみ講? 怪しい契約をしてしまった場合の対処法
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
ねずみ講は、法律上違法な取引として禁止されており、ねずみ講に加入して、他人を勧誘してしまうと、ご自身も刑事罰を受ける可能性がありますので注意が必要です。
今回は、ねずみ講の典型例や解約方法、被害相談窓口などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、ねずみ講とは何か
そもそもねずみ講とはどのようなものなのでしょうか。以下では、ねずみ講の定義と典型例などについて説明します。
-
(1)ねずみ講とは?
ねずみ講とは、正式名称を「無限連鎖講」といい、加入者が2人以上の人を勧誘し、勧誘された人がさらに2人以上の人を勧誘することでピラミッド式に会員が増える組織です。多産のねずみがどんどん子孫を増やす様子になぞらえて、「ねずみ講」と呼ばれています。
具体的には、以下のような組織は、ねずみ講と判断されます。- 金品を出す加入者が無限に増加するとして、
- 先に入った加入者が、2人以上の人を後から勧誘し、
- 先に入った加入者が、後に入った人が支払った金品から、自分が支払った金品の価額を上回るものを受け取る
たとえば、最初の会員が新たに5人を勧誘して加入させ、その5人がさらに5人ずつ新たに勧誘して加入させるような仕組みです。加入時に1万円を支払ったとしても、5人を勧誘することで、5万円が手に入りますので、最初に支払った1万円を差し引いたとしても、4万円が手元に残ることになります。
加入者を増やせば増やすほど利益が出る仕組みになっていますが、人数には限りがあります。この例でいえば12代目で日本の人口を超過しますので、破綻を前提としたビジネスとなっています。 -
(2)ねずみ講が禁止される発端となった事件|天下一家の会事件
ねずみ講が禁止される発端となった事件は、天下一家の会事件という日本最大規模のねずみ講事件です。
この事件では、「4人の子会員を勧誘すれば、約2000円が約100万円になる」と言って、多くの会員を勧誘し、全国から100万人以上の会員と約1900億円ものお金を集めました。
当時は、ねずみ講を禁止する法律がなかったため、簡単にお金を増やすことができる仕組みに釣られて、多くの人がねずみ講に参加してしまいました。
しかし、ねずみ講は、いずれ破綻する性質の組織ですので、天下一家の会も、その後配当ができなくなり破綻して、多数の被害者が発生することになりました。
2、マルチ商法との違い
ねずみ講と似た仕組みに「マルチ商法」というものがあります。以下では、ねずみ講とマルチ商法との違いについて説明します。
-
(1)マルチ商法とは
マルチ商法とは、特定商取引上の正式名称を「連鎖販売取引」といい、個人を販売員として勧誘し、さらにその人に別の販売員を勧誘させて、連鎖的に販売組織を拡大させるビジネスです。
たとえば、保証金を支払って会員になれば高性能の浄水器を購入できるようになり、それを他の人に売って会員を増やすことでマージンが得られるなどの取引がマルチ商法に該当します。 -
(2)ねずみ講とマルチ商法の違い
ねずみ講とマルチ商法とでは、主に以下のような違いがあります。
① 違法か合法かの違い
ねずみ講は、無限連鎖講防止法により禁止されており、ねずみ講を開設・運営した人や勧誘をした人に対しては、刑事罰が科されます。
マルチ商法は、特定商取引法の規制を受けますが、ねずみ講のように一律禁止されているわけではありません。勧誘方法などが厳しく規制されていますが、要件を満たせば合法的に行うことができます。
② 取引目的の違い
ねずみ講とマルチ商法は、会員を増やすことで利益を上げることができるという点で共通します。
しかし、ねずみ講は、金銭の配当を得ることのみを目的として行われるものであるのに対して、マルチ商法は商品やサービスの販売を伴うものであるという点で異なります。わかりやすく言えば、商品を介さずにもっぱら金銭のやり取りで成り立っているのがねずみ講です。
3、ねずみ講は解約できる?
ねずみ講の勧誘を受けて加入してしまった場合、解約をすることはできるのでしょうか。
-
(1)そもそもねずみ講は無効
ねずみ講に加入する契約は、公序良俗に反しますので、無効とされています(長野地方裁判所昭和52年3月30日判決、判時849号33頁)。
そのため、契約の無効を主張することにより勧誘者からの請求を拒否することができ、基本的には支払い済みの金銭についても返還請求をすることが可能です。
ただし、違法なねずみ講であると明確に認識して加入し、金銭を支払った場合や、加入後、他人を勧誘するなどして自身も利益を得ていたような場合には、ねずみ講という公序良俗に反する不法な原因でお金を支払ったとして、支払済みの金銭の返還を求めることができないおそれがあるため、注意が必要です。
なお、マルチ商法については、ねずみ講とは異なり、法律上の要件を満たせば法的に有効な取引になりますので、その場合には直ちに無効を主張することはできません。しかし、一定期間内であれば特定商取引法に基づくクーリングオフを利用することにより、理由を問わず契約を解約することができます。 -
(2)人を勧誘してしまうと自身も処罰対象になる可能性あり!
ねずみ講に勧誘されて加入したとしても、それだけで処罰されることはありません。
しかし、ねずみ講に加入した後に自分も他人を勧誘してしまうと、無限連鎖講防止法違反となり、20万円以下の罰金が科されます。また、業としてねずみ講への勧誘をすると、1年以下の懲役または30万円以下の罰金という重い刑罰が科されます。
1回でも勧誘すれば無限連鎖講防止法違反となりますので、うまいもうけ話に誘われたときは、違法なねずみ講を疑った方がよいでしょう。ご自身では判断できないときは、早めに弁護士への相談をおすすめします。
4、ねずみ講被害を相談できる窓口
ねずみ講による被害を受けたときは、以下のような窓口で相談できます。
-
(1)行政窓口
ねずみ講による被害を相談できる行政窓口としては、各都道府県や市区町村に設置されている消費生活センターがあります。
消費生活センターでは、専門的知識と経験を有する消費生活相談員が契約トラブル、悪質商法、多重債務などの消費者問題全般についての相談に対応してくれます。
トラブル解決に向けたアドバイスを無料で受けることができますので、ねずみ講によるトラブル解決に役立つでしょう。 -
(2)警察
警察への相談も方法のひとつです。警察が相談内容を聞き、無限連鎖講防止法違反が疑われると判断すれば、捜査が行われるでしょう。その場合、ねずみ講を始めた人や会社が刑事的な処罰を受ける可能性もありますが、ご自身の支払ったお金を警察が取り返してくれることはありません。
警察の捜査はあくまで刑事事件として行われるものであり、お金を取り戻すためには、別途民事事件として損害賠償請求等をする必要があるからです。
また、ご自身がすでにねずみ講に参加し他の人を勧誘して法に触れている場合には、ご自身も罪に問われる可能性があります。その場合は警察よりも先に弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士であれば、不当に重い罪にならないよう、活動することができるからです。 -
(3)弁護士
ねずみ講による被害回復をお考えの方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談をすることで、ねずみ講によるトラブル解決に向けたアドバイスをしてもらうことができるだけでなく、被害者の代理人として勧誘者やねずみ講開設者に対して、返金交渉をすることができます。
行政窓口での相談では解決に向けたアドバイスは受けられますが、実際に交渉するのは基本的に被害者自身です。不慣れな方では、相手との交渉が負担に感じるかもしれません。
弁護士に依頼をすれば、相手との交渉をすべて任せることができるため、ご自身の負担を大幅に軽減できるとともに、返金を受けられる可能性を高めることができます。
多数の被害者がいるねずみ講では、返金してもらうには早期に対応することが重要になります。ねずみ講の被害に遭った場合には、すぐに弁護士に相談するようにしてください。
5、まとめ
ねずみ講は、無限連鎖講防止法により禁止されていますので、公序良俗を理由として、契約の無効を主張することができます。また、無限連鎖講防止法では、ねずみ講開設者や勧誘者に対して、刑事罰を定めていますので、ねずみ講に加入後、誰かを勧誘してしまうと自分も刑事処分を受ける可能性がありますので注意が必要です。
もしねずみ講に勧誘されて困っている、ねずみ講を契約してしまったといったトラブルがありましたら、早めに弁護士に相談しましょう。
なお、ベリーベスト法律事務所では、有料にはなりますが、ねずみ講被害に関するご相談を承っていますので、お困りの方は当事務所までご相談ください。
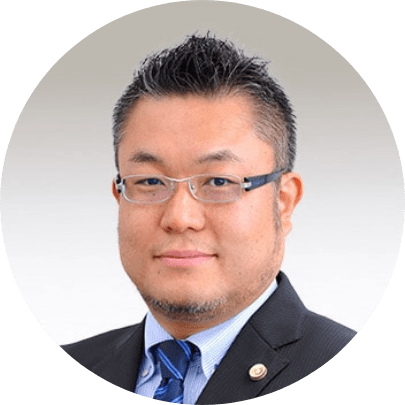
消費者トラブルへの知見が豊富な消費者問題専門チームの弁護士が問題の解決に取り組みます。
マルチ商法や霊感商法、悪徳商法などをはじめとした消費者トラブルでお困りでしたら、ぜひ、お気軽にご相談ください。