- 消費者問題について弁護士に相談
- 弁護士コラム
- 電話で詐欺に遭ってしまった! まず何をすればいい? お金は戻ってくる?
電話で詐欺に遭ってしまった! まず何をすればいい? お金は戻ってくる?
監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)
そのような詐欺被害に遭わないためにもまずはどのような詐欺の手口があるのかを理解し、詐欺被害にあってしまったときの対処法を覚えておきましょう。
今回は、電話詐欺の手口や電話詐欺の被害にあったときの対処法などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
1、多種多様な電話詐欺。そのパターンをいくつか紹介
電話を使った詐欺の手口には、さまざまなものがあり、年々のその手口は巧妙化しています。以下では、よくある電話詐欺のパターンを紹介します。
-
(1)オレオレ詐欺
親族、警察官、弁護士などを装い、家族が起こした事件や事故に対する示談金名目で金銭をだまし取る手口です。知らない電話番号から着信があり、「会社のお金を横領した。」、「事故を起こした。」などを理由に「至急示談金が必要。」などと言われたときは注意が必要です。
-
(2)還付金詐欺
医療費、年金、税金などが還付されると偽り、被害者をATMに移動させ、口座間送金をさせる手口です。自治体、年金事務所、税務署の職員を名乗って、還付金を受け取れる旨告げられたときは注意が必要です。
-
(3)預貯金詐欺
親族、警察官、銀行協会の職員などを装い、口座が犯罪に利用されておりキャッシュカードの交換が必要になったと告げて、被害者からキャッシュカードや預貯金通帳をだまし取る手口です。
口座が犯罪に利用されていたとしても、警察や銀行協会の職員が直接自宅にやってきて預貯金通帳やキャッシュカードを預かることはありませんので、覚えておきましょう。 -
(4)キャッシュカード詐欺
警察官、銀行協会、大手百貨店などの職員を装い、被害者に電話をかけて、キャッシュカードが不正利用されているなどの名目で、カードを準備させ、対面している最中に、被害者の隙を見てそのカードを盗む手口です。
被害者には、あらかじめ準備しておいた偽のカードを渡すなどして、口座から現金を引き出してしまいます。 -
(5)架空料金請求詐欺
未払い料金があるなど架空の事実を告げて金銭をだまし取る手口です。
架空の料金を請求するメールやショートメッセージ(SMS)が届き、記載された電話番号に連絡すると「すぐに支払わなければ裁判になる」などと不安をあおり、冷静な判断ができない状態にしてきます。
2、もし電話で詐欺に遭ったことがわかった場合、最初にするべきこととは
もし電話で詐欺に遭ったことがわかったときは、すぐに以下のような対応をしましょう。
-
(1)警察に連絡する
電話で詐欺に遭ったことがわかったときは、すぐに警察に連絡をしましょう。
その際、まだ犯人との連絡が続いているようであれば、警察から「だまされた振り作戦」への協力を求められることもあります。
だまされた振り作戦とは、詐欺に気付いていてもだまされた振りをして、犯人が利用している電話番号や預貯金口座の番号を聞き出したり、犯人をおびき出して逮捕する方法です。
詐欺被害撲滅のために必要な対応になりますので、可能な範囲で協力するようにしましょう。 -
(2)電話番号や会話を録音して証拠保全をする
犯人との電話中に詐欺であることに気付いたときは、犯人との会話を録音しておくことで、警察に相談する際の証拠として利用することができます。
また、犯人からかかってきた電話番号画面はすぐに削除するのではなく、可能であればスクリーンショットをとるなどして証拠保全に努めましょう。
3、3つの機関に相談して、これ以上の被害を防ごう
電話で詐欺に遭ったときに相談できる機関としては、以下の3つが挙げられます。それぞれ異なる役割がありますので、必要な機関に相談して詐欺被害の拡大を防ぎましょう。
-
(1)警察
電話による詐欺によりお金をだまし取られてしまったときは、すぐに警察に連絡をしましょう。特殊詐欺被害に関しては、専用の相談窓口が設けられていますので、まずは「#9110」に電話をして、今後の対応についてアドバイスしてもらうとよいでしょう。全国どこからでも、その地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります。
また、電話の途中で詐欺に気付いて具体的な被害に遭わなかったとしても、警察に連絡しておいた方がよいでしょう。
なぜなら、電話による詐欺は、特定地域に集中して行われることもあるため、警察に連絡をしておけば、地域の注意喚起になるからです。 -
(2)金融機関
電話による詐欺の被害に遭い、犯人の指示に従って預金口座などに振り込みをしてしまったときは、被害回復分配金の支払いのために金融機関に連絡をしてください。
振り込め詐欺救済法は、銀行口座などへの振り込みを使った犯罪行為の被害者救済を目的とした法律です。犯罪行為で利用された口座を凍結し、その残高や被害額に応じて、被害回復分配金の支払いを行っています。
犯人が口座からお金を引き出した後では、被害回復分配金の支払いを受けられなくなってしまいますので、電話による詐欺に気付いたときはすぐに振込先の金融機関に連絡をするようにしましょう。 -
(3)弁護士
電話による詐欺被害に遭ったときは、弁護士に相談をすることも有効な手段です。
警察は、詐欺事件として捜査をしてくれますが、あくまでも犯人を検挙するのが目的ですので、被害者がだまし取られたお金を取り戻してはくれません。犯人からお金を取り戻すには、民事訴訟などの手続きをする必要がありますが、弁護士であれば代理人として訴訟手続きのサポートを行うことができます。
また、詐欺事件として刑事告訴するのは自分でもできますが、弁護士に依頼すれば、代理人となった弁護士が告訴状の作成や警察への説明などを行いますので、スムーズに捜査に着手してもらうことができます。
電話による詐欺の被害回復を自分でやろうとすると、二次被害に遭うリスクもあります。専門家である弁護士に相談してサポートしてもらうとよいでしょう。
4、電話詐欺を含む詐欺を防ぐ対策とは
電話詐欺を含む詐欺を防ぐためには、以下のような対策が有効です。
-
(1)電話詐欺を未然に防ぐ具体的な対策
電話詐欺を未然に防ぐのに有効な対策としては、主に以下のような対策が挙げられます。
① 家族で合言葉を決めておく
オレオレ詐欺のように家族を装った詐欺の手口があります。電話口だと声が不明瞭であるため家族以外の人からの電話であっても声だけでは気付けないこともありますので、家族で合言葉を決めておくことが有効な対策です。
家族で決めた合言葉が答えられないようであれば、詐欺である可能性が高いため、すぐに電話を切って警察に連絡をしましょう。
② 留守番電話にしておく
電話詐欺の対策として、留守番電話を設定しておくことも有効な対策です。
詐欺グループの犯人は、自分の声が録音されるのを嫌う傾向がありますので、留守番電話に切り替わるとすぐに電話を切ることが多いです。他方、本当に要件がある人であれば留守番電話にメッセージを残すはずです。
知らない番号から電話がきた場合、すぐに電話に出るのではなくメッセージを聴いてから折り返す習慣をつけておくとよいでしょう。
③ お金の話が出たら電話を切る
電話でお金やキャッシュカードなどに関する話題が出てきたら、一度電話を切るようにしましょう。
詐欺の犯人は、巧みな話術で被害者をだまそうとしてきますので、電話で話を聞き続けているとどんどん相手のことを信用してしまいます。
不安をあおられ、冷静な判断ができない状態になると詐欺に気付くことができませんので、一度冷静になるためにも電話を切るようにしてください。
そうすれば怪しい電話だと気付くことができ、詐欺被害を回避できる可能性が高くなります。 -
(2)高齢家族が詐欺にあうのが心配な場合の対策
詐欺は、特に高齢者が被害に遭うケースが多いです。高齢の家族が詐欺に遭うのが心配なら以下のような対策を検討しましょう。
① 離れているところに住んでいるなら頻繁にコミュニケーションをとる
高齢の家族が離れたところに住んでいる場合、詐欺の被害にあってもすぐに気付けず、多額の被害が生じるケースがあります。詐欺被害の拡大を防ぐためにも、普段から頻繁にコミュニケーションをとり、家族の様子の変化に気付けるようにしておくことが大切です。
お互いに気軽にコミュニケーションがとれる状況であれば、何かおかしなことがあれば、高齢の家族の方から連絡をしてくれるでしょう。
② 補助、保佐、後見の制度利用を検討する
高齢者になると認知症などにより判断能力が低下していきます。十分な判断能力がない状態では、詐欺師に簡単にだまされてしまい、大切な財産を失ってしまいます。
そのようなリスクを回避するには、補助、保佐、後見といった法定後見制度の利用を検討してみるとよいでしょう。法定後見制度とは、判断能力が不十分な本人を保護する制度であり、裁判所により選任された後見人などが、財産管理や身上監護などの支援を行うことができます。
高齢の本人を守るための非常に有効な手段ですので、本人の判断能力の程度に応じて利用を検討してみましょう。
③ お金を使うルールを決めておく
高齢者による詐欺被害を防ぐには、お金を使う際のルールを決めておくことも有効な対策になります。- 電話でお金の話がでたら切る
- ○○万円以上の支払いについては必ず家族に相談する
- ○○万円以上の支払いをしたときは家族に報告する
このようなルールを定めておくことで詐欺被害の防止や拡大を防ぐことができます。
5、まとめ
電話を利用した詐欺の手口は、年々巧妙化しており、誰でも詐欺の被害に遭う可能性があります。詐欺被害に遭わないように日頃からしっかりと対策しておくとともに、万が一詐欺被害にあってしまったときは迅速に対処することが大切です。
電話による詐欺の被害に遭ってしまった方は、被害を回復できる可能性がありますので、早めにベリーベスト法律事務所までご相談ください(ご相談は有料です)。
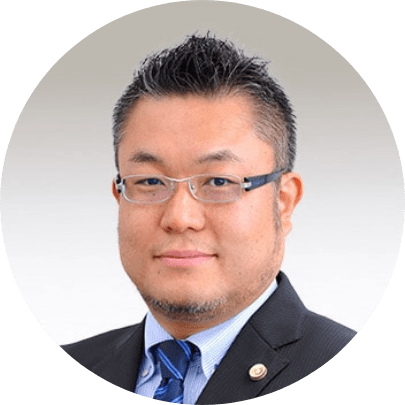
消費者トラブルへの知見が豊富な消費者問題専門チームの弁護士が問題の解決に取り組みます。
マルチ商法や霊感商法、悪徳商法などをはじめとした消費者トラブルでお困りでしたら、ぜひ、お気軽にご相談ください。